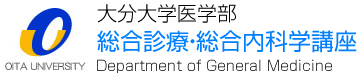今回は外部より講師を招き、函館稜北病院 川口 篤也先生より「ACP(アドバンス・ケア・プランニング)」についてのご講演をいただきました。
川口 篤也先生は同病院総合診療医として、在宅医療や介護連携などをはじめ様々なフィールドで精力的にご尽力され、ACPに関しても多数ご講演をされておられます。
まずはACPの成り立ちやその概念などからお話いただきました。ACP・DNAR・事前指示などの概念は正しく理解し適切に行うことが重要ですが、今回しっかりとお話を聴けたので自分の頭の中を整理することができました。
先生が実際に診療されている患者さんの事例紹介や取り組みを交えながらACPについて学べましたが、個人的には「ACPを話し合う機を逃さない」というお言葉が印象的でした。
これまで元気だったから今後の話をした事などなかったけれど、いざ重大な疾患に罹ってしまい今後のことを考えなければならなくなった際にどうしたら良いか分からなくなる…また、家族同士で、最期に過ごしたい場所や受けたい医療のことなどについて話し合うのは気恥ずかしくてできないなどといったケースはよく経験します。
川口先生のポイントとして、誕生日を迎えたタイミングで今後どう過ごしたいか尋ねてみる、患者さんやご家族がなんとなく話をしたそうにしている「間」を逃さない、告知直後など頭が真っ白になっているであろうタイミングは避け少し落ち着いたタイミングで話をしてみる、などの助言をいただきました。早速実臨床でも試してみたいと思います。
また、一つの施設でACPを完結させるのではなく、複数の施設で連続して話し合いを続け、移り変わっていく患者さんやご家族の意思を聴取し続けることが重要であることや、ACPは「一点」の話ではなくプロセスであり、ingであることなど、貴重なお話を多く聴くことができました。実際に、川口先生が使用されているカルテ上のACPについての記載も拝見でき大変参考になりました。
川口先生が登場キャラのモデルになっておられる、在宅診療を描いた漫画「はっぴーえんど」、ぜひ読んでみようと思います。
末尾となりますが、川口先生、大変お忙しい中貴重なご講演をいただきまして、誠にありがとうございました。今後とも、何卒宜しくお願い申し上げます。
文責:堀之内 泰雄 拝