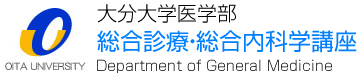7月18日に第3回専攻医勉強会が開催され、マインドフルネス・セルフコンパッションについて、京都大学大学院医学研究科 健康増進・行動学分野客員研究員の岸本早苗先生からご講義を賜りました。
岸本先生は当科 堀之内 登先生の京都大学大学院に所属していた時にお世話になっていたとのことでその御縁で今回の勉強会が実現しました。マインドフルネスとはストレスマネジメントの一つで自分自身が自分自身の痛みをこころがけてあげることができるようにする方法です。慢性疼痛等に対するストレスフルな体験に対して受容的な関係になることでそのストレスを軽減でき、それに対するランダム化比較試験を先生が実際に行っておりその効果が実証されています。
患者様を向き合い、相手を理解するにはまず医療従事者自身が自分自身を知り、自分の体験を理解することが重要です。さらにその体験自体が昨今急増している医療従事者のバーンアウト予防につながるとされています。同様にセルフコンパッションについても非常に興味深いお話をいただきました。セルフコンパッションとは、友人や心から愛する人と同じように自分自身をケアすることであり、実践により自分の健やかさや幸せのために長期的なスパンで行動できるようになるとされており、心の資産形成と言われています。
今まで困難な症例に対して、患者さんのことに対して様々考えることは多かったのですが、まず自分の抱えているストレスなどの感情を十分気づき、まず自分自身に対して思いやりを持って行動してこそよりよい対応につながっていくと講義で知ることができました。
これらのことは非常に新鮮であり、明日からの診療に大いに活用することができると思いました。ご講義の最後には質問コーナーも設けられ、活発な議論が行われました。末筆ではございますが、岸本先生、貴重なご講義、ご指導を賜りありがとうございました。
文責 後藤 亮