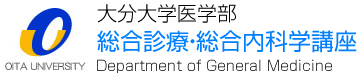第3-6回 Common diseases輪読会を開催しました。いずれもzoomを用いてオンラインで開催され、専攻医の先生方による活発な議論が行われました。
第3回は8月4日に行われ、第17章「COPD」、第18章「気管支喘息」を扱いました。オブザーバーとして、アルメイダ病院総合診療科 石井稔浩先生にご参加いただきました。これらの疾患はCommon diseasesではありますが、初期研修や2次医療機関での後期研修では外来での長期管理に携わってきた経験が乏しく、質問には基本的に石井先生からお答えいただく形式となりました。同効の吸入薬の使い分けや各吸入薬の使用感、FeNO・喀痰好酸球検査など少し専門的な検査の位置づけなど、プライマリケアで必要な知識を呼吸器内科専門医の先生から学べる貴重な機会となりました。
第4回は9月8日に行われ、第32章「糖尿病」、第33章「脂質異常症」を扱いました。これらの分野については1-2年目の専攻医でもそれなりの臨床経験があり、これまでで最も活発なDiscussionだったように思います。ガイドラインが目まぐるしく変更され、なんとなく治療されることもある本分野ですが、大分大学医学部附属病院総合診療科 土井恵里先生から現場での治療の実際を伺うことができ、実臨床に活かせる知識を身に着けられました(糖尿病薬の選択や75歳以上のスタチン導入など)。
第5回は10月13日に行われ、第10章「HFrEF」、第11章「HFpEF」を扱いました。オブザーバーとしては、大分三愛メディカルセンター総合診療科 堤大輔先生にご参加いただきました。高齢化に伴って有病率が増加し、国民病とも呼ばれる心不全診療は、今やプライマリケア医が避けて通れないものとなっています。堤先生からは、HFrEFの薬物治療の実際や心エコー検査で気を付ける項目などの医学的知識に加えて、専門医頼りではなく自らでできる限りの診療を行い、その幅を広げていくことの重要性を熱く教えていただきました。
第6回は11月10日に行われ、第22章「NAFLD」、第23章「肝硬変」、第24章「アルコール性肝障害」を扱いました。各々の専攻医が、健診やクリニックでの診療で頻繁にみられる肝胆道系酵素上昇への対応に悩みを抱えていましたが、オブザーバーの津久見中央病院総合診療科 堀之内登先生に一つ一つ丁寧に解説いていただきました。また、津久見市の地域柄、肝炎や肝硬変症例でも専門的治療が不要であれば非専門医が診療にあたっていると伺い、先述の心不全同様に自らの土俵を広げることの意義をより実感することができました。
いずれの回も、ご参加いただいた専攻医の先生方には非常に満足していただける会になった思います。遅筆によりまとめての実施報告となってしまったことをお詫び申し上げます。
次回は12月8日、大分大学医学部附属病院 吉村亮彦先生をお招きし、第42章「尿路感染症」、第47章「伝染性単核球症」、第49章「帯状疱疹」を扱います。たくさんの専攻医の先生方のご参加を楽しみにしております。
<Common diseases輪読会>
●日時:毎月第2木曜日 18時30分~
●内容:Commom Diseases Up to date 南山堂
当日はよくわからなかったところ、印象に残ったところをピックアップし、自分の経験と照らし合わせながらの振り返りを含めてディスカッションを行います。
文責 筒井 勇貴